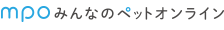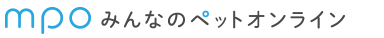猫の下痢ってどういう状態?

健康な便に含まれる水分率は70~80%ほどで、しっかりした形があり、持っても形が崩れません。
下痢とは、正確には水分の多い便の排泄のことですが、これに加えてやや柔らかい便や、頻繁に便をして排便回数が増える状態も、下痢として扱われます。
おおまかに2~3日以内に急に下痢をするようになった場合が「急性」で、治療をおこなっても2~3週間続くものが「慢性」の下痢とされ、原因や治療方法、治療にかかる期間はさまざまです。
急性の下痢の原因として代表的なものに、異物誤飲、寄生虫、食事内容の問題、消化不良、感染症があります。
慢性の下痢では原因を特定するのが難しいケースも多く、膵炎、腸炎、炎症性腸疾患(IBD)、腫瘍など難治性の疾患が隠れている場合もあります。
下痢とは、正確には水分の多い便の排泄のことですが、これに加えてやや柔らかい便や、頻繁に便をして排便回数が増える状態も、下痢として扱われます。
おおまかに2~3日以内に急に下痢をするようになった場合が「急性」で、治療をおこなっても2~3週間続くものが「慢性」の下痢とされ、原因や治療方法、治療にかかる期間はさまざまです。
急性の下痢の原因として代表的なものに、異物誤飲、寄生虫、食事内容の問題、消化不良、感染症があります。
慢性の下痢では原因を特定するのが難しいケースも多く、膵炎、腸炎、炎症性腸疾患(IBD)、腫瘍など難治性の疾患が隠れている場合もあります。
猫の下痢にはどんな種類があるの?

軟便
便に含まれる水分量が通常よりやや多く、柔らかく崩れやすい半固形状の便を軟便といいます。
手や紙でつかむことが難しく、トイレ本体、猫砂などにべたべたとくっついてしまいます。
手や紙でつかむことが難しく、トイレ本体、猫砂などにべたべたとくっついてしまいます。
水様便
水分が90%以上含まれている、ほぼ液状の便が水様便です。
水分が多い分、1回の排泄量が多くなることもありますが、腹痛や排便時の不快感から、少量の便を頻回で排泄する場合もあります。
水分が多い分、1回の排泄量が多くなることもありますが、腹痛や排便時の不快感から、少量の便を頻回で排泄する場合もあります。
粘液便
粘液便は、便が粘液に包まれていたり、付着していたりする状態の便です。
粘液は、腸粘膜から分泌されるタンパク質の一種であり、ある程度は健康な猫の便にも付着しています。
ただし、ゼリーのように目に見える量の場合には、何らかの異常が疑われ、正常の硬さの便に付着することもあれば、軟便や水様便に混ざることもあります。
粘液は、腸粘膜から分泌されるタンパク質の一種であり、ある程度は健康な猫の便にも付着しています。
ただし、ゼリーのように目に見える量の場合には、何らかの異常が疑われ、正常の硬さの便に付着することもあれば、軟便や水様便に混ざることもあります。
血便、血様便、黒色便
血液が混ざった便を血便または血様便といいます。肛門から近い部位の大腸や、肛門での出血は、血液が排出されるまでの時間が短いため、血液が赤い色のまま排泄物に付着します。
一方、黒色便は、血液中のヘモグロビンが消化酵素などの作用によって変色し、黒色に変化し排泄されたものをいいます。食道や胃、小腸、十二指腸までの消化管の上部で出血が起きているときに排泄されることが多いです。タール様便またはメレナ、下血と呼ばれることもあります。
一方、黒色便は、血液中のヘモグロビンが消化酵素などの作用によって変色し、黒色に変化し排泄されたものをいいます。食道や胃、小腸、十二指腸までの消化管の上部で出血が起きているときに排泄されることが多いです。タール様便またはメレナ、下血と呼ばれることもあります。
猫の下痢の原因

誤飲・誤食
紐やゴムなどの異物を飲み込むことで消化管を傷つけたり、腸閉塞になったりし、下痢や嘔吐を引き起こす場合があります。
また、殺虫剤や観葉植物など、猫にとって有害なものを口にしてしまったときも下痢につながる可能性があるため要注意です。
また、殺虫剤や観葉植物など、猫にとって有害なものを口にしてしまったときも下痢につながる可能性があるため要注意です。
アレルギー
肉食動物の猫にとってタンパク質は欠かせませんが、素材によってはアレルギーの原因となり、下痢の症状がみられます。
以前から問題なく食べ慣れてきた素材でも、突然、アレルギー反応を起こすこともあるので注意しましょう。
以前から問題なく食べ慣れてきた素材でも、突然、アレルギー反応を起こすこともあるので注意しましょう。
消化不良
ごはんの食べ過ぎや新しいフードへの切り替え、脂肪分や特定の種類の食物繊維の取りすぎなどが原因で、消化器官への刺激が大きくなり、下痢をすることがあります。
薬
なんらかの病気で抗生物質を使っている場合、腸内の細菌バランス(腸内細菌叢)が崩れ、おなかがゆるくなることがあります。
ストレス
猫は繊細な動物なので、ストレスによって体調を崩しがちです。
とくに、引っ越しや部屋の模様替え、家族構成の変化、犬や猫などの新しいペットの増加といった環境の変化はストレスになりやすく、下痢などの消化器症状が表れるケースも多くみられます。
とくに、引っ越しや部屋の模様替え、家族構成の変化、犬や猫などの新しいペットの増加といった環境の変化はストレスになりやすく、下痢などの消化器症状が表れるケースも多くみられます。
内臓や内分泌の病気
なんらかの病気に罹患している場合、症状の一つとして下痢の症状が表れます。
消化器の病気
膵炎、肝炎、胆管炎、胃腸炎、炎症性腸疾患(IBD)などの消化器系の病気では、下痢は典型的な症状の一つです。
肝炎や胆管炎では黄疸も出ることがあり、胃腸炎や炎症性腸疾患では血便が出ることも。膵炎では、腹部の痛みから元気が消失し、触られるのを嫌がる場合もあります。
肝炎や胆管炎では黄疸も出ることがあり、胃腸炎や炎症性腸疾患では血便が出ることも。膵炎では、腹部の痛みから元気が消失し、触られるのを嫌がる場合もあります。
悪性腫瘍
悪性腫瘍が発生した部位によって、下痢の症状が表れることがあります。
とくに腸腺がんや消化器型のリンパ腫では下痢になることが多く、食欲低下や体重減少により元気が消失し、嘔吐などの症状も起こります。
また、抗がん剤の副作用として、消化器粘膜の細胞が破壊されることにより、下痢になる場合もあります。
とくに腸腺がんや消化器型のリンパ腫では下痢になることが多く、食欲低下や体重減少により元気が消失し、嘔吐などの症状も起こります。
また、抗がん剤の副作用として、消化器粘膜の細胞が破壊されることにより、下痢になる場合もあります。
内分泌の病気
甲状腺機能亢進症など内分泌系の病気も、下痢をする可能性があります。甲状腺機能亢進症は内分泌の一つである甲状腺の動きが活発になることで、全身に悪影響を及ぼす病気です。
呼吸が荒くなり、興奮しやすく活動量が増えて、次第に痩せてきます。食欲も増進しますが、消化機能が低下し、下痢をしてしまいます。
呼吸が荒くなり、興奮しやすく活動量が増えて、次第に痩せてきます。食欲も増進しますが、消化機能が低下し、下痢をしてしまいます。
感染症
細菌
ウエルシュ菌やカンピロバクター、大腸菌が過剰に増えることにより腸内細菌のバランスが崩れると、下痢を引き起こします。
また、病原性大腸菌やサルモネラ菌に汚染された食物や、捕獲した野生の鳥・ネズミなどを食べることで感染して、下痢になる場合もあります。
また、病原性大腸菌やサルモネラ菌に汚染された食物や、捕獲した野生の鳥・ネズミなどを食べることで感染して、下痢になる場合もあります。
ウイルス
重篤な全身症状を引き起こす猫エイズウイルスや猫白血病ウイルスのほかに、猫パルボウイルスや猫コロナウイルスに感染したときにも、下痢の症状が表れます。
なお、猫コロナウイルスは、新型コロナウイルスとは分類が異なるウイルスです。
なお、猫コロナウイルスは、新型コロナウイルスとは分類が異なるウイルスです。
寄生虫
トキソプラズマ、コクシジウム、ジアルジアなどの原虫や、回虫、条虫が消化管に寄生することで、下痢を引き起こします。
子猫は下痢をしがち

子猫は生まれてからしばらくは母猫の乳だけを栄養にしていますが、月齢によって少しずつ食べるものが変わります。成長に伴って少しずつ消化能力が備わっていくため、便の形も変化しやすいものです。
ここでは、子猫特有の下痢について紹介します。
ここでは、子猫特有の下痢について紹介します。
子猫の下痢の原因
授乳期の子猫の場合、人が与えるミルクの温度が冷たいと、下痢の原因につながります。また、ミルクの濃度が適正でないときも、消化不良によって下痢を引き起こす可能性があります。
猫にとって牛乳は消化しにくいため、子猫に与えるミルクは子猫専用のものを選び、用法や容量に合った濃度で人肌程度に温めてあげるようにしましょう。
離乳食をはじめたばかりの時期、キャットフードに完全に切り替えた時期では、消化能力が不十分なため下痢をしがちです。このようなタイミングでの下痢は、体の成長に伴って減少していきます。
下痢をしていても元気であれば、いったん離乳食をやめてミルクに戻すか、離乳食を減らしてミルクの割合を増やし、数日ほど様子を見る場合もあります。
猫にとって牛乳は消化しにくいため、子猫に与えるミルクは子猫専用のものを選び、用法や容量に合った濃度で人肌程度に温めてあげるようにしましょう。
離乳食をはじめたばかりの時期、キャットフードに完全に切り替えた時期では、消化能力が不十分なため下痢をしがちです。このようなタイミングでの下痢は、体の成長に伴って減少していきます。
下痢をしていても元気であれば、いったん離乳食をやめてミルクに戻すか、離乳食を減らしてミルクの割合を増やし、数日ほど様子を見る場合もあります。
猫が下痢をしたときの対処法

成猫の場合
愛猫が下痢をしている場合、行動の様子や便の状態をよく観察します。
下痢や軟便をしていても、症状が激しくなく元気があるときは、1回の食事量を減らしたり、食事を小分けにしたりして、1日程度は様子を見るのもよいでしょう。
ただし、以下のような症状があれば、できるだけ早く動物病院に連れて行ってください。
下痢や軟便をしていても、症状が激しくなく元気があるときは、1回の食事量を減らしたり、食事を小分けにしたりして、1日程度は様子を見るのもよいでしょう。
ただし、以下のような症状があれば、できるだけ早く動物病院に連れて行ってください。
- 下痢の量や回数が多い
- 食欲がない
- 嘔吐している
- 体重が減っている
- 便の色がどす黒い、または鮮血が混ざっている
- 数日様子を見ていたが改善しない
- 元気がなくぐったりして、皮膚に張りがない
- 伝染病や寄生虫に感染した可能性がある
子猫の場合
子猫の場合も、まずは便の状態と行動を観察します。
体が未熟な子猫は、激しい下痢が続くと脱水症状に陥りやすく、命に関わります。
症状が軽い、下痢をしているが元気はあるという場合でも、早めに病院に連れて行き、獣医師の指示を仰ぎましょう。
体が未熟な子猫は、激しい下痢が続くと脱水症状に陥りやすく、命に関わります。
症状が軽い、下痢をしているが元気はあるという場合でも、早めに病院に連れて行き、獣医師の指示を仰ぎましょう。

人間用の下痢止めを与えるのはNG
高野 航平先生
猫が下痢をしたときはストレスをかけないことが大切なので、いつもの環境を変化させず、落ち着ける場所をつくってあげてください。
また、猫に人間の下痢止めを飲ませることはしないでください。人と猫では体重も大きく異なり、代謝の作用も異なるので、猫の体や症状に合わないことがあります。
必ず動物病院で処方された薬を与えるようにしましょう。
また、猫に人間の下痢止めを飲ませることはしないでください。人と猫では体重も大きく異なり、代謝の作用も異なるので、猫の体や症状に合わないことがあります。
必ず動物病院で処方された薬を与えるようにしましょう。
愛猫の苦しむ下痢を予防するには

部屋の環境を整える
猫は暖かい場所を好むため、過ごしやすい部屋の温度を保つことが大切です。冷え込む季節は暖房を使い、春から秋の過ごしやすい季節でも寒暖差に注意しましょう。
また、室内はこまめに清掃し、ゴミやほこりがたまらないように、誤飲・誤食につながりそうなものは撤去します。
とくに漂白剤や洗剤に含まれる界面活性剤は猫の消化器官を傷つけてしまうので、舐めたり飲んだりしないよう片付けてください。
そのほかに家の外と中を自由に出入りしている猫は、外から感染症を持ち帰ることがあります。猫の健康と安全のために、室内で飼育するようにしましょう。
また、室内はこまめに清掃し、ゴミやほこりがたまらないように、誤飲・誤食につながりそうなものは撤去します。
とくに漂白剤や洗剤に含まれる界面活性剤は猫の消化器官を傷つけてしまうので、舐めたり飲んだりしないよう片付けてください。
そのほかに家の外と中を自由に出入りしている猫は、外から感染症を持ち帰ることがあります。猫の健康と安全のために、室内で飼育するようにしましょう。
「あげてはいけない食べ物」を与えない
長ねぎ、玉ねぎ、にんにく、エシャロットなどのねぎ類は、猫が重度の貧血を起こす可能性があり、危険です。絶対に与えないようにしましょう。
また、生肉の種類にもよりますが、鶏肉や豚肉は大腸菌やサルモネラ菌など病原菌に感染する危険性が高く、下痢の原因となります。
そのほか、過剰な量の野菜や硬い骨を与えると、消化不良による下痢を引き起こすことがあります。
キャットフードや猫用おやつであっても、量を間違えると消化不良によって下痢になるので、適切な量を与えるようにしてください。
また、生肉の種類にもよりますが、鶏肉や豚肉は大腸菌やサルモネラ菌など病原菌に感染する危険性が高く、下痢の原因となります。
そのほか、過剰な量の野菜や硬い骨を与えると、消化不良による下痢を引き起こすことがあります。
キャットフードや猫用おやつであっても、量を間違えると消化不良によって下痢になるので、適切な量を与えるようにしてください。
キャットフードを変える
猫が食物アレルギーを起こす原因として食物中のタンパク質があげられ、アレルギーをきっかけに腸炎を起こし、嘔吐や下痢をする場合があります。
食物アレルギーを起こしている原因の食べ物を検査し、その種類が分かれば、それを除去したフードに変更することが望まれます。
食物アレルギーを起こしている原因の食べ物を検査し、その種類が分かれば、それを除去したフードに変更することが望まれます。
ワクチンを接種する
猫の伝染病のうち、猫汎白血球減少症(別名:猫伝染性腸炎、猫パルボウィルス感染症)は、下痢の症状から脱水が進み、放置すると死に至ることもある病気です。
3種混合ワクチンで予防できるので、定期的に接種してあげましょう。
なお、予防接種にはアレルギーやアナフィラキシーを引き起こす可能性があります。
ワクチン接種後、元気消失、顔や体の腫れ、発赤、湿疹、嘔吐、下痢などが起こったら、すぐに動物病院で受診してください。
3種混合ワクチンで予防できるので、定期的に接種してあげましょう。
なお、予防接種にはアレルギーやアナフィラキシーを引き起こす可能性があります。
ワクチン接種後、元気消失、顔や体の腫れ、発赤、湿疹、嘔吐、下痢などが起こったら、すぐに動物病院で受診してください。

猫にストレスを与えない工夫を
高野 航平先生
環境面での変化を少なくして、猫にストレスをかけないことが下痢の予防につながります。
猫が過ごしやすいように部屋を適切な温度に調整することを心がけ、異物誤飲をしないためにも部屋は清潔に保つようにしましょう。
また、汚れたトイレで排泄したがらないため、トイレを常にきれいにすることも大事です。
そのほか、いつもと異なるフードやおやつを与えるときは、一気に与えず、猫の様子を見ながら少量ずつ与えてくださいね。
外に出られるようにしてしまうと、ほかの猫や動物と接触することでウイルスや寄生虫感染症のリスクも高くなるので、室内飼いをしましょう。
猫が過ごしやすいように部屋を適切な温度に調整することを心がけ、異物誤飲をしないためにも部屋は清潔に保つようにしましょう。
また、汚れたトイレで排泄したがらないため、トイレを常にきれいにすることも大事です。
そのほか、いつもと異なるフードやおやつを与えるときは、一気に与えず、猫の様子を見ながら少量ずつ与えてくださいね。
外に出られるようにしてしまうと、ほかの猫や動物と接触することでウイルスや寄生虫感染症のリスクも高くなるので、室内飼いをしましょう。
獣医師に聞いた! 猫の下痢に関するQ&A
猫が下痢のとき、市販の人間用の整腸剤(ビオフェルミンなど)を与えても大丈夫?
動物病院では、猫にビオフェルミンなどの整腸剤を処方することもありますが、飼い主さんの判断で、人間用の整腸剤を与えることはしないでください。
獣医師が、猫の体重と症状から整腸剤の種類や量を調整して処方していますので、必ず動物病院で出された薬を与えるようにしましょう。
獣医師が、猫の体重と症状から整腸剤の種類や量を調整して処方していますので、必ず動物病院で出された薬を与えるようにしましょう。
猫の避妊・去勢手術が終わってから下痢が続いている。原因や対処法は?
避妊・去勢手術をおこなう際は、全身麻酔や絶水絶食の実施により、猫の体に大きな負担がかかります。そのため、術後に食欲不振などの症状や、処方された薬の影響により下痢のような消化器症状が表れることもあります。なかには、脱水やほかの臓器に負担がかかることが原因で症状が悪化し、2日以上続くケースもあるでしょう。
術後に下痢の症状が出たら、当日か翌日以内などの早期に、手術を受けた病院へ相談するようにしてください。
術後に下痢の症状が出たら、当日か翌日以内などの早期に、手術を受けた病院へ相談するようにしてください。
元気はあるけど下痢をしている。どのタイミングで病院に連れて行くべき?
猫が下痢をしたら、できるだけ早めに通院するのが望ましいです。ただ、猫に大きなストレスがかかる、どうしても早期に通院できないという場合は、猫の年齢により通院の目安が異なります。
3~4カ月以内の子猫の場合は、1日様子を見るだけでも、脱水や低血糖に陥りやすいため、当日中の受診が望まれます。
それ以上の月齢や年齢の場合ですが、猫は元気に見えても、痛みや違和感の症状を飼い主さんに見せずに、隠して生活することもあります。遅くても翌日までには通院するようにしてください。
3~4カ月以内の子猫の場合は、1日様子を見るだけでも、脱水や低血糖に陥りやすいため、当日中の受診が望まれます。
それ以上の月齢や年齢の場合ですが、猫は元気に見えても、痛みや違和感の症状を飼い主さんに見せずに、隠して生活することもあります。遅くても翌日までには通院するようにしてください。
猫が下痢のときはフードをふやかして与えたほうがいい?
下痢のときは脱水しやすいため、キャットフードをふやかして与えることで、自動的に体内に水分を摂取することができます。ただし、ふやかしたフードは好き嫌いが別れるため、食べないようでしたらドライフードのままのほうがよい場合もあります。
また、水分を含むウェットフードはドライフードよりも香りが立ち食欲を刺激します。下痢のときは、ウェットフードをメインで与えてもいいですし、両方置いて好きなほうを選んで食べてもらう方法もあります。
また、水分を含むウェットフードはドライフードよりも香りが立ち食欲を刺激します。下痢のときは、ウェットフードをメインで与えてもいいですし、両方置いて好きなほうを選んで食べてもらう方法もあります。
獣医師からのメッセージ
猫が下痢にならないためには、過ごしやすいように家の環境を整え、異物誤飲がないように部屋を清潔にすることが大切です。また、日ごろの食事内容にも気を付けましょう。
下痢だけでなく、ほかの病気の予防のためにワクチン接種をおこない、室内飼いしてあげることも重要です。それでも下痢をしてしまったら、考えられる原因を一つずつ除去したうえで、早めに通院し、かかりつけの先生の指示に従って治療をおこないましょう。
経過が長いほど猫に負担がかかりますので、早く症状が治まるように適切な治療を受けてください。
下痢だけでなく、ほかの病気の予防のためにワクチン接種をおこない、室内飼いしてあげることも重要です。それでも下痢をしてしまったら、考えられる原因を一つずつ除去したうえで、早めに通院し、かかりつけの先生の指示に従って治療をおこないましょう。
経過が長いほど猫に負担がかかりますので、早く症状が治まるように適切な治療を受けてください。
まとめ

猫の下痢には、飼い主の工夫と対策で予防できるものもあれば、病気に伴って表れる症状や、治療が難しい下痢もあります。
言葉を話せない猫にとって、下痢は体調悪化の重要なサイン。避けられない結果の下痢でも、適切な対処をすることで、愛猫のつらい症状を軽減できることもあります。
様子を見ているうちに体調が悪化することもありますので、改善しないときは早めに動物病院に行きましょう。
言葉を話せない猫にとって、下痢は体調悪化の重要なサイン。避けられない結果の下痢でも、適切な対処をすることで、愛猫のつらい症状を軽減できることもあります。
様子を見ているうちに体調が悪化することもありますので、改善しないときは早めに動物病院に行きましょう。