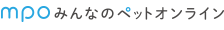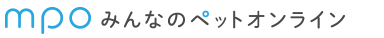血統書とは

血統書とは、「血統証明書」を略したもので、人間の「戸籍謄本」のような書類です。
血統書には、本猫、両親、祖父母、曾祖父母の情報が記載されていて、本猫から3代前の祖先まで、すべて同一猫種であることが証明されます。
※3代祖以上の情報が載っている場合もあります
血統書には、本猫、両親、祖父母、曾祖父母の情報が記載されていて、本猫から3代前の祖先まで、すべて同一猫種であることが証明されます。
※3代祖以上の情報が載っている場合もあります
血統書はいつ使う?
血統書は、その猫の血統を証明する書類のため、健康状態や優劣などが分かるものではありません。
キャットショーに出陳したり、ブリーダーとして猫を交配したりするときには血統書が必要ですが、ペットとして飼育している一般の飼い主であれば、血統書を使う場面はほとんどないのです。
キャットショーに出陳したり、ブリーダーとして猫を交配したりするときには血統書が必要ですが、ペットとして飼育している一般の飼い主であれば、血統書を使う場面はほとんどないのです。
猫の血統書の見方

血統書に書かれている主な情報
猫の血統書発行団体によって、血統書に記載される内容は多少異なりますが、主に以下の内容について書かれています。
そのほか、スコティッシュフォールドやアメリカンカールなど、耳の形状によって交配の可否が決まる猫種については、耳の形状について記載されることもあります。
- 猫名
- 登録番号
- 猫種
- 性別
- 毛色
- 目の色
- 生年月日
- 繁殖者名(ブリーダー名)
- 所有者名
- 登録年月日
- 血統欄
そのほか、スコティッシュフォールドやアメリカンカールなど、耳の形状によって交配の可否が決まる猫種については、耳の形状について記載されることもあります。
チャンピオン、称号の記載がある場合も
両親や祖先のなかで、キャットショーにおいてチャンピオンやグランドチャンピオンなどを獲得したことのある猫がいれば、その旨も記載されます。
(記載例)
CH.:チャンピオン
GC.:グランドチャンピオン
PR.:プレミア(避妊去勢のクラス)
GP.:グランドプレミア
(記載例)
CH.:チャンピオン
GC.:グランドチャンピオン
PR.:プレミア(避妊去勢のクラス)
GP.:グランドプレミア
繁殖者【ブリーダー】の情報がわかる
血統書に記載されている「繁殖者」とは、その猫を繁殖し、育てたブリーダーのことです。ペットショップなどで子猫をお迎えし、「どんな人が愛猫を育ててくれたのかわからない……」という場合でも、血統書に書かれているブリーダーの名前をインターネットなどで検索することで、そのブリーダーを見つけられるかもしれません。
ブリーダー自身についての情報や、ブリーディングに対する想いが載っている子猫お迎えサイトもあるので、チェックしてみるとよいでしょう。
『みんなの子猫ブリーダー』では、以下のような情報が見られるほか、サイト内でブリーダーに対して出産予定などの問い合わせもできます。
「今いる愛猫を育てたブリーダーさんから、2頭目を迎えたい!」「愛猫と血のつながりのある子を探したい」という方は、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
【みんなの子猫ブリーダーで確認できる情報】
『みんなの子猫ブリーダー』でブリーダーを検索してみる
ブリーダー自身についての情報や、ブリーディングに対する想いが載っている子猫お迎えサイトもあるので、チェックしてみるとよいでしょう。
『みんなの子猫ブリーダー』では、以下のような情報が見られるほか、サイト内でブリーダーに対して出産予定などの問い合わせもできます。
「今いる愛猫を育てたブリーダーさんから、2頭目を迎えたい!」「愛猫と血のつながりのある子を探したい」という方は、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
【みんなの子猫ブリーダーで確認できる情報】
- 猫舎紹介
- 取り扱い猫種
- 猫舎所在地
- 猫舎見学についてのご案内
- 猫舎の口コミや評価
『みんなの子猫ブリーダー』でブリーダーを検索してみる
猫の血統書の名義変更、再発行

猫の血統書を発行している団体
猫の血統書は、数多くの団体から発行されています。
アメリカを本拠地とする世界最大の血統登録機関であるTICA(The International Cat Association)やCFA(Cat Fanciers’ Association)をはじめとして、その大規模団体に所属するクラブや支部が世界中に存在しており、犬と比べると発行団体の数は非常に多いです。
日本では、JCC(Japan Cat Club)、ICC(International Cat Club)などの団体で血統書が発行されています。
ブリーダーは自身が登録している団体へ血統書の申請をおこない、発行してもらいます。
なお、血統書を発行する際に、「Not For Breeding(繁殖しない)」「Not For Showing(ショーに出さない)」といった項目にチェックを求められることもあります。「Not For Breeding(繁殖しない)」にチェックを入れる場合は、血統書は避妊手術をおこなった後に発行されるのが一般的です。
アメリカを本拠地とする世界最大の血統登録機関であるTICA(The International Cat Association)やCFA(Cat Fanciers’ Association)をはじめとして、その大規模団体に所属するクラブや支部が世界中に存在しており、犬と比べると発行団体の数は非常に多いです。
日本では、JCC(Japan Cat Club)、ICC(International Cat Club)などの団体で血統書が発行されています。
ブリーダーは自身が登録している団体へ血統書の申請をおこない、発行してもらいます。
なお、血統書を発行する際に、「Not For Breeding(繁殖しない)」「Not For Showing(ショーに出さない)」といった項目にチェックを求められることもあります。「Not For Breeding(繁殖しない)」にチェックを入れる場合は、血統書は避妊手術をおこなった後に発行されるのが一般的です。
名義変更しなくても問題ない
猫をお迎えしたときは、血統書にある所有者の欄は、基本的にブリーダーの名前が記載されています。猫をペットとして飼うのであれば、所有者の名義変更をおこなわなくても不都合はありません。
ただし、以下の場合は、血統書の名義を購入者へと変更する必要があります。
名義変更をおこなう場合は、発行団体への加入・登録が必要です。また、名義変更をする際に費用がかかるケースもあります。
ただし、以下の場合は、血統書の名義を購入者へと変更する必要があります。
- キャットショーに出ることを考えている
- ブリーダーとして自分で猫を交配・繁殖させる予定である
名義変更をおこなう場合は、発行団体への加入・登録が必要です。また、名義変更をする際に費用がかかるケースもあります。
再発行が可能
血統書が紛失・破損した場合、その猫が登録されている団体にて再発行可能ですが、申請方法などは団体によって異なります。
血統書発行団体によっては、名義変更の手続きが済んでいる場合のみ再発行可能としているところも……。子猫をお迎えした際に、発行団体のホームページなどを事前に確認しておくとよいでしょう。
血統書発行団体によっては、名義変更の手続きが済んでいる場合のみ再発行可能としているところも……。子猫をお迎えした際に、発行団体のホームページなどを事前に確認しておくとよいでしょう。
まとめ

猫をペットとして飼うのであれば使う機会の少ない血統書ですが、祖先をたどることもできる興味深い書類です。
また、ブリーダーや猫舎名の情報を入力することで、きょうだい猫や親戚猫を探せるサイトもあります。愛猫のルーツを調べたり、多頭飼いを検討したりする場合は、血統書を活用するのも一つの手かもしれません。
また、ブリーダーや猫舎名の情報を入力することで、きょうだい猫や親戚猫を探せるサイトもあります。愛猫のルーツを調べたり、多頭飼いを検討したりする場合は、血統書を活用するのも一つの手かもしれません。