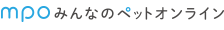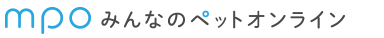ジェネッタの特徴

大きさ
小さめの猫で、体重は3~6kgほどです。
長めの胴としっぽ、短い足という特徴的な見た目の猫ですが、なかには長足の子も存在します。
長めの胴としっぽ、短い足という特徴的な見た目の猫ですが、なかには長足の子も存在します。
性格
好奇心旺盛で、とても活発な性格。短い足ながら、動きはとても俊敏です。
人懐こく友好的で、子どものいる家庭にもすぐに順応します。家族に対して愛情深く接する猫ですが、警戒心が強く慎重な一面も持ち合わせています。
人懐こく友好的で、子どものいる家庭にもすぐに順応します。家族に対して愛情深く接する猫ですが、警戒心が強く慎重な一面も持ち合わせています。
毛色
ベースの毛色はブラウンやシルバー、スノー、ブラックなど。そこに、ヒョウ柄のようなスポテッド、マーブルといった模様が入ります。
平均価格
当サイトでのジェネッタの平均価格は、オスが約12万円、メスが約15万円、全体では約13万円です。
販売中のジェネッタの子猫を見る
ジェネッタの飼い方

しつけ
飼い主に対して愛情深いので、しつけで苦労することは少ないようです。アクティブな性格を生かし、遊びながらしつけるのもよいでしょう。
好奇心旺盛で、いたずらには注意が必要です。触れてほしくないものや、猫にとって危険なものは、あらかじめ片付けておいてください。
繊細な面もあるため、生活音に慣れさせることも覚えておきたいところ。また、猫が驚くようなシチュエーションをできるだけつくらないことで、脱走などのトラブルを回避することができます。
好奇心旺盛で、いたずらには注意が必要です。触れてほしくないものや、猫にとって危険なものは、あらかじめ片付けておいてください。
繊細な面もあるため、生活音に慣れさせることも覚えておきたいところ。また、猫が驚くようなシチュエーションをできるだけつくらないことで、脱走などのトラブルを回避することができます。
お手入れ
ブラッシング
ブラッシングはできるだけ毎日、少なくとも週に2~3回を目安におこなってください。
短毛で抜け毛もそこまで多くはないので、お手入れは比較的簡単です。春と秋の換毛期には抜け毛が多くなるので、抜け毛の量に合わせてブラッシングの頻度を調整するとよいでしょう。
短毛で抜け毛もそこまで多くはないので、お手入れは比較的簡単です。春と秋の換毛期には抜け毛が多くなるので、抜け毛の量に合わせてブラッシングの頻度を調整するとよいでしょう。
シャンプー
基本的に、シャンプーは必要ありません。猫自身でグルーミングをしており、とくに短毛種であるジェネッタは、日ごろのブラッシングで十分に清潔感を維持できます。
汚れやにおいが気になるとき、換毛期で抜け毛が多いときなど、必要に応じてシャンプーをしてあげてください。シャンプーは、多くても月に1回程度。頻度が多すぎると、皮膚トラブルの原因になるので注意しましょう。
汚れやにおいが気になるとき、換毛期で抜け毛が多いときなど、必要に応じてシャンプーをしてあげてください。シャンプーは、多くても月に1回程度。頻度が多すぎると、皮膚トラブルの原因になるので注意しましょう。
歯磨き
歯磨きは毎日おこなうのが理想。少なくとも2~3日に1回はケアするようにしましょう。
猫の場合、たまった歯垢は1週間ほどで歯石化してしまいます。また、歯石化すると歯磨きでは取り除くことができません。日ごろから歯をケアして予防することが大切です。
猫の場合、たまった歯垢は1週間ほどで歯石化してしまいます。また、歯石化すると歯磨きでは取り除くことができません。日ごろから歯をケアして予防することが大切です。
爪切り
日ごろから爪の長さをチェックし、2週間~1カ月に1回程度は切ってあげます。
爪とぎをする猫に、爪切りは必要ないように感じますが、爪とぎで爪を短くすることはできません。爪切りをせずに放置していると、長い爪がひっかかって爪が折れたり、肉球に刺さってケガをしたりすることも。また、飼い主が猫に引っかかれてケガをする可能性もあります。
爪とぎをする猫に、爪切りは必要ないように感じますが、爪とぎで爪を短くすることはできません。爪切りをせずに放置していると、長い爪がひっかかって爪が折れたり、肉球に刺さってケガをしたりすることも。また、飼い主が猫に引っかかれてケガをする可能性もあります。
ジェネッタを飼う際の注意点

肥満
よく動き回りジャンプ力もありますが、足が短いため、足腰に負担がかかりがちです。肥満になると体が重くなって余計に負担がかかるので、食事管理や体重管理はしっかりおこなう必要があります。
アクティブな様子を見るとエネルギー消費量が高いと思って、食事の量を増やしたり、おやつをたくさん与えたくなったりするかもしれません。カロリーオーバーにならないよう、愛猫の大きさや年齢を考慮しながら、食事やおやつの量を調節してくださいね。
アクティブな様子を見るとエネルギー消費量が高いと思って、食事の量を増やしたり、おやつをたくさん与えたくなったりするかもしれません。カロリーオーバーにならないよう、愛猫の大きさや年齢を考慮しながら、食事やおやつの量を調節してくださいね。
遊ぶ環境を整える
ジェネッタは、遊ぶことが大好きで運動量を多く必要とする猫です。ストレスがたまらないように遊ぶ環境を整え、一緒に遊ぶ時間もつくってあげましょう。
猫が大好きなキャットタワーは、関節に負荷のかからない段差が低いタイプがおすすめです。また、床が滑りやすい場合は滑り止めマットやカーペットなどを敷いてあげてください。
猫が大好きなキャットタワーは、関節に負荷のかからない段差が低いタイプがおすすめです。また、床が滑りやすい場合は滑り止めマットやカーペットなどを敷いてあげてください。
ジェネッタがかかりやすい病気、寿命

注意したい病気
椎間板ヘルニア
胴長短足の猫は胴への負担が大きくなり、椎間板ヘルニアになりやすいため注意が必要です。事故やケガによる外傷のほか、加齢や肥満が原因になる場合もあります。
痛みが生じることで動きたがらない、歩行にふらつきが出るといった症状が表れます。症状が軽度の場合は、鎮痛剤や炎症止めの薬で治療しますが、症状の改善が見られない場合、あるいは症状が重度の場合は手術やレーザー治療がおこなわれます。
痛みが生じることで動きたがらない、歩行にふらつきが出るといった症状が表れます。症状が軽度の場合は、鎮痛剤や炎症止めの薬で治療しますが、症状の改善が見られない場合、あるいは症状が重度の場合は手術やレーザー治療がおこなわれます。
健康寿命を延ばすために
交配に用いられた猫種の平均寿命は、ベンガルとマンチカンが14歳前後、サバンナキャットが17~20歳です。
新しい猫種で寿命に関するデータは少ないですが、作出する際に用いた猫種から推測すると、ジェネッタの平均寿命は12~15歳くらいであると考えることができます。
愛猫を長生きさせるには、お手入れや食事管理、飼育環境の整備などをしっかりおこなうことが大切です。
新しい猫種で寿命に関するデータは少ないですが、作出する際に用いた猫種から推測すると、ジェネッタの平均寿命は12~15歳くらいであると考えることができます。
愛猫を長生きさせるには、お手入れや食事管理、飼育環境の整備などをしっかりおこなうことが大切です。
毎日の運動
好奇心旺盛で活発な猫種で、遊ぶのが大好きです。ストレスがたまらないように十分な飼育スペースを確保し、一緒に遊ぶ時間をつくってあげるとよいでしょう。
ひとりでも遊べるように、おもちゃを用意するのもおすすめです。
ジェネッタは足腰に負担のかかりやすい胴長短足の体形であるため、遊ぶ際にケガをしないように注意しましょう。
ひとりでも遊べるように、おもちゃを用意するのもおすすめです。
ジェネッタは足腰に負担のかかりやすい胴長短足の体形であるため、遊ぶ際にケガをしないように注意しましょう。
食事の管理
体重が増えすぎると、足腰への負担が大きくなってしまいます。
体重と年齢に合った食事量で体重管理を徹底し、おやつの与えすぎにも気を付けてください。
体重と年齢に合った食事量で体重管理を徹底し、おやつの与えすぎにも気を付けてください。
安全な環境づくり
高い所から下りるときや、走ったりジャンプしたりしたときに滑らないような環境づくりも大切です。
キャットタワーは段差が低いものを選び、フローリングなどの滑りやすい場所にはマットやラグを敷いてあげるとよいでしょう。
関連する記事
キャットタワーは段差が低いものを選び、フローリングなどの滑りやすい場所にはマットやラグを敷いてあげるとよいでしょう。
ジェネッタのルーツ
誕生の経緯
ジェネッタの誕生は、アフリカンジェネットという野生動物に似た猫を作出したいという愛好家の思いがはじまりです。
アフリカンジェネットは、アフリカや南ヨーロッパに生息するジャコウネコ科の肉食動物。ヒョウのような柄の被毛に長いしっぽ、体は細長く、足が短いのが特徴です。
交配に用いたのは、アフリカンジェネットに似た特徴を持つ猫種。マンチカンやベンガル、サバンナキャット、オリエンタルショートヘアなどをかけ合わせてジェネッタが誕生しました。
アフリカンジェネットは、アフリカや南ヨーロッパに生息するジャコウネコ科の肉食動物。ヒョウのような柄の被毛に長いしっぽ、体は細長く、足が短いのが特徴です。
交配に用いたのは、アフリカンジェネットに似た特徴を持つ猫種。マンチカンやベンガル、サバンナキャット、オリエンタルショートヘアなどをかけ合わせてジェネッタが誕生しました。
まとめ

ワイルドさとかわいらしさを兼ね備えたジェネッタは、好奇心旺盛で家族にも愛情深く、飼いやすい猫です。新しい猫種で、ほかの猫種と比べると情報が少ない傾向にありますが、分からないことや不安な点はブリーダーに相談すること、愛猫の様子をしっかり観察することで楽しい猫ライフを送ることができます。ぜひ、今回の記事も参考にしてみてくださいね。