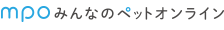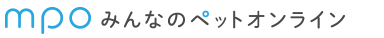猫のための災害対策

住環境の安全対策
まずは、家の中の安全対策からはじめます。家具は倒れてこないように転倒防止処置をとり、食器棚の扉が開いたり引き出しが飛び出したりしないよう、ストッパーグッズの取り付けをおこないましょう。
窓ガラスの飛散防止対策も重要です。とくに愛猫のお気に入りの場所は、倒れてくるものがないように安全な状態にします。
窓ガラスの飛散防止対策も重要です。とくに愛猫のお気に入りの場所は、倒れてくるものがないように安全な状態にします。
災害に備えた猫のしつけ
社会化をおこなう
毎日の散歩がない猫にとって、社会性を身に付けるというのはなかなか難しいこと。しかし、避難所など慣れない場所でできるだけストレスを感じずに過ごしてもらうには、社会化が必要になります。
病院やトリミングサロン、来客時などを利用して、飼い主以外の人やほかの動物に慣れてもらうように意識しましょう。
病院やトリミングサロン、来客時などを利用して、飼い主以外の人やほかの動物に慣れてもらうように意識しましょう。
ケージやキャリーバッグに慣らす
猫のなかには、ケージやキャリーバッグは「病院に行くときに入れられる」というイメージをもつ子もいて、警戒してしまうものになりがちです。防災を考えるとそれはよいことではありません。
日ごろからキャリーに慣れさせて、いざというときにスムーズに避難できるようにしましょう。
普段過ごす場所として、あえて家の中に設置して使用するのも効果的です。ケース上部がハードタイプであれば、いざというときに家の中での避難場所にもなります。
日ごろからキャリーに慣れさせて、いざというときにスムーズに避難できるようにしましょう。
普段過ごす場所として、あえて家の中に設置して使用するのも効果的です。ケース上部がハードタイプであれば、いざというときに家の中での避難場所にもなります。
猫の健康管理の徹底
避妊・去勢手術
災害時に猫だけが自宅に取り残されてしまったり、避難中にはぐれてしまったりしたときに、未避妊・未去勢の猫だと心配事が増える可能性があります。
たとえば、発情期のメス猫のにおいを追いかけてそのまま行方不明になるケースや、メス猫の場合、見つかっても妊娠して帰ってくるというケースが考えられます。
また、避妊・去勢手術をすると、性的ストレスの軽減や病気の予防などにつながります。同行避難をして慣れない環境での生活が続く場合に、愛猫の心身の健康を守ることにも役立つでしょう。
手術を受けておくことで、災害時に起こり得るトラブルを未然に防ぐことができます。
たとえば、発情期のメス猫のにおいを追いかけてそのまま行方不明になるケースや、メス猫の場合、見つかっても妊娠して帰ってくるというケースが考えられます。
また、避妊・去勢手術をすると、性的ストレスの軽減や病気の予防などにつながります。同行避難をして慣れない環境での生活が続く場合に、愛猫の心身の健康を守ることにも役立つでしょう。
手術を受けておくことで、災害時に起こり得るトラブルを未然に防ぐことができます。
ワクチン接種、寄生虫予防
ワクチン接種や寄生虫の駆除が済んでいない猫の場合、避難所やペットシェルターに入れないことがあります。自宅で預かってくれるという個人ボランティアも、感染症対策をおこなっていることを前提にしている場合がほとんどです。
多くの人が集まる場所で、感染症をうつさない・うつされないためにもきちんと受けておきましょう。
多くの人が集まる場所で、感染症をうつさない・うつされないためにもきちんと受けておきましょう。
猫の行方不明対策
首輪と迷子札の装着
首輪を装着していると、迷子になっても保護される可能性が高くなります。瞬時に誰かの飼い猫であることがわかり、身分証明書代わりにもなります。
保護されたときにすぐに連絡がくるよう、迷子札に飼い主の電話番号を記しておきましょう。
保護されたときにすぐに連絡がくるよう、迷子札に飼い主の電話番号を記しておきましょう。
マイクロチップの装着・登録情報の確認
災害時、猫だけが自宅にいるという状況や、途中で離れ離れになることを想定すると、猫の所有者(飼い主)判明にはマイクロチップがもっとも有効です。保健所や警察、動物病院、または避難所に設置されるマイクロチップリーダーで番号を読み取り、登録情報を照会し、飼い主へ知らせます。
マイクロチップをすでに装着させているという方も、最新の飼い主情報が登録されているか確認しましょう。
マイクロチップをすでに装着させているという方も、最新の飼い主情報が登録されているか確認しましょう。
愛猫の写真を用意しておく
写真があると、はぐれてしまったときに愛猫を探しやすくなります。スマートフォンやカメラのなかのデータだけでなく、もしものことを想定し、1枚だけでもよいのでプリントして持っておきます。
猫だけ写っているもののほかに、飼い主と一緒に写っているものも用意しておくと、飼い主を特定するのに役立ちます。
猫だけ写っているもののほかに、飼い主と一緒に写っているものも用意しておくと、飼い主を特定するのに役立ちます。
ワクチン接種状況や既往歴の記録
避難所でワクチン接種証明書を求められることがあるかもしれません。また、避難中に猫が体調不良になり、動物病院を受診しなければならない可能性もあります。
ワクチン接種証明書のほか、既往歴、飲んでいる薬があればお薬手帳など、スムーズに情報提供できるようにしておくと安心です。停電時や紛失する場合に備えて、スマートフォンでのメモと手書きのメモ、両方あるとなおよいでしょう。
ワクチン接種証明書のほか、既往歴、飲んでいる薬があればお薬手帳など、スムーズに情報提供できるようにしておくと安心です。停電時や紛失する場合に備えて、スマートフォンでのメモと手書きのメモ、両方あるとなおよいでしょう。
猫の避難グッズで必要なもの

災害発生時に慌てずに済むよう、事前に愛猫用の「非常用持ち出し袋」を準備しましょう。
持ち出し袋の中に入れるべき避難グッズについて、絶対に必要なものから、あれば役立つものまで、環境省のガイドラインを参考に紹介します。
持ち出し袋の中に入れるべき避難グッズについて、絶対に必要なものから、あれば役立つものまで、環境省のガイドラインを参考に紹介します。
猫用の非常用持ち出し袋
避難所などの避難先に、ペット用の救援物資が届くまでには時間がかかることがあります。
防災グッズは、ライフラインが止まった状態での生活を想定し、5日分程度用意しておきましょう。
防災グッズは、ライフラインが止まった状態での生活を想定し、5日分程度用意しておきましょう。
参考文献
人とペットの災害対策ガイドライン<一般飼い主編>(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h3009a/a-1a.pdf)
【優先順位1】命や健康に関わるもの
薬、療法食
持病の薬がある場合は、獣医師と相談し、可能であれば多めに処方してもらうとよいでしょう。念のため、薬名と服用方法はメモで残しておくのがおすすめです。
療法食も、災害時に入手困難となりそうなものは普段から多めにストックしておきます。
薬と療法食は消費期限に注意して、普段から消費しながら備蓄しましょう。
療法食も、災害時に入手困難となりそうなものは普段から多めにストックしておきます。
薬と療法食は消費期限に注意して、普段から消費しながら備蓄しましょう。
フード、水
ドライフードは栄養バランスがとれており、軽いため、非常用としておすすめです。
ウエットフードは、水分を一緒に摂取できるというメリットがあります。重さに余裕があればどちらも用意しておくとよいでしょう。
また、避難所でペット用の水をもらえないこともあるので、愛猫用に軟水や純水を用意します。
消費期限が切れていたということにならないよう、期限があるものは日常生活で消費しながら備蓄します。いずれも5日分以上は用意しましょう。
ウエットフードは、水分を一緒に摂取できるというメリットがあります。重さに余裕があればどちらも用意しておくとよいでしょう。
また、避難所でペット用の水をもらえないこともあるので、愛猫用に軟水や純水を用意します。
消費期限が切れていたということにならないよう、期限があるものは日常生活で消費しながら備蓄します。いずれも5日分以上は用意しましょう。
キャリーバッグやケージ
避難所までの移動のほか、避難先で就寝場所としても使用できる重要な防災グッズです。両手が空くリュックタイプや、肩かけ、タイヤをコロコロと転がして運ぶカートタイプもあります。
予備の首輪、伸びないタイプのリード
首輪またはハーネス、リードは愛猫の安全を確保できる重要アイテムです。首輪やハーネスは猫の体にフィットするものを、リードは伸びないタイプを選び、可能であれば数本用意しましょう。
普段から装着し、慣れさせておくと、いざというときスムーズに動けます。
普段から装着し、慣れさせておくと、いざというときスムーズに動けます。
ペットシーツ
ペットシーツは本来の用途だけでなく、愛猫のマナーベルト、人間用の簡易トイレや赤ちゃんのオムツなどにも使える万能グッズ。
持ち出し用だけでなく、自宅にも多めにストックしておくと安心です。
持ち出し用だけでなく、自宅にも多めにストックしておくと安心です。
排泄物の処理用具
猫砂用のスコップと防臭効果のあるビニール袋も必要です。
つい忘れがちなグッズですが、防臭ビニール袋はさまざまな活用方法があるので、数十枚入りのものを用意しておくとよいでしょう。
つい忘れがちなグッズですが、防臭ビニール袋はさまざまな活用方法があるので、数十枚入りのものを用意しておくとよいでしょう。
トイレ用品
猫砂は愛猫が普段使っているものがおすすめ。ペットシーツ同様、いざというときは人間用としても使えます。
トイレはポータブル可能な折り畳み式や軽量タイプなどもありますが、段ボール箱を利用して猫用トイレを作るのも一つの手です。
トイレはポータブル可能な折り畳み式や軽量タイプなどもありますが、段ボール箱を利用して猫用トイレを作るのも一つの手です。
食器
可能であれば水用とフード用で一つずつ入れておくと役立ちます。
コンパクトタイプ、折りたためるタイプ、使い捨てなど、さまざまな種類があります。
コンパクトタイプ、折りたためるタイプ、使い捨てなど、さまざまな種類があります。
【優先順位2】ペットや飼い主の情報
- 飼い主の連絡先
- ペットの写真
- ワクチン接種状況や既往歴、投薬中の薬情報、かかりつけの動物病院など
避難中に愛猫が体調不良になったとき、愛猫とはぐれてしまったときなどに役立つものです。
ワクチン接種状況は、避難時にチェックされる可能性もあります。どちらの情報も、スマートフォンでのメモと手帳などへの手書きのメモの両方あると安心です。
【優先順位3】ペット用品
- タオル、ブラシ
- ウェットティッシュや清浄綿
- ビニール袋
- お気に入りのおもちゃなど匂いがついたグッズ
- 洗濯ネット(屋外診療や保護のときに使用)
- ガムテープ、マジック
タオルやウェットティッシュ、ビニール袋などのペット用品は、さまざまなシーンで活用できる便利グッズです。たとえば、ライフラインが止まっていたり、水の使用に制限がかかっていたりするときに、食器洗いやトイレ掃除をする際にウェットティッシュが役立ちます。
細々したものはすべて、雨で濡れてしまわないよう、チャックなどで密閉できるタイプのビニール袋に小分けしておきましょう。
災害が発生したら

安全確保
まずは自分の身の安全を確保します。
これは非常に重要なことで、愛猫を守るためにも飼い主さんは無事でいなければなりません。地震の場合であれば、安全な場所に移動し、身を守りましょう。
次に愛猫の保護です。愛猫を落ち着かせるよう努め、移動用のケージなどに入れましょう。
猫が怖がっていたりパニックになっていたりして捕まえるのが難しいときは、ブランケットなどで背後から包み込むように抱き上げます。
可能であれば、ハーネスやリードをケージの中で装着します。
これは非常に重要なことで、愛猫を守るためにも飼い主さんは無事でいなければなりません。地震の場合であれば、安全な場所に移動し、身を守りましょう。
次に愛猫の保護です。愛猫を落ち着かせるよう努め、移動用のケージなどに入れましょう。
猫が怖がっていたりパニックになっていたりして捕まえるのが難しいときは、ブランケットなどで背後から包み込むように抱き上げます。
可能であれば、ハーネスやリードをケージの中で装着します。
情報収集と避難準備
電気のブレーカーとガスの元栓を切ります。
その後、室内のガラス飛散や倒れた家具に注意をして避難の準備をします。スニーカーなど外靴を履いて行動するとよいでしょう。
地震の場合はドアを開け、避難経路を確保します。
次にスマートフォンやラジオなどで情報収集します。
避難の指示があった場合は、愛猫の安全に気を配りながら速やかに避難しましょう。
避難の際は、愛猫を入れているケージやバッグの扉が開いてしまわないよう、ガムテープなどで固定するのがよいです。
その後、室内のガラス飛散や倒れた家具に注意をして避難の準備をします。スニーカーなど外靴を履いて行動するとよいでしょう。
地震の場合はドアを開け、避難経路を確保します。
次にスマートフォンやラジオなどで情報収集します。
避難の指示があった場合は、愛猫の安全に気を配りながら速やかに避難しましょう。
避難の際は、愛猫を入れているケージやバッグの扉が開いてしまわないよう、ガムテープなどで固定するのがよいです。
災害後に猫と暮らす際の注意点

避難所の場合
ペット可の避難所でも、ペットと飼い主が必ず同じスペースで過ごせるわけではありません。ペットは専用の飼育スペースにクレートやケージを設置し、飼い主はその場所へ都度お世話をしに行く、というところがほとんどです。
避難所にはペットを飼っていない人や、猫アレルギーがある人、動物が嫌いな人もいます。避難所にいる全員が安全に快適に過ごせるよう、各避難所が定めたルールに従いましょう。
避難所にはペットを飼っていない人や、猫アレルギーがある人、動物が嫌いな人もいます。避難所にいる全員が安全に快適に過ごせるよう、各避難所が定めたルールに従いましょう。
自宅の場合
自宅とその周辺の安全確認ができたら、在宅避難となります。家屋倒壊や二次災害の心配がなければ、住み慣れた自宅で過ごすのが愛猫にとってもおすすめです。
最寄りの避難所で避難者としての登録を済ませ、自宅で過ごしながら、ライフラインの復旧を待ちましょう。水は給水拠点や配給車から、救援物資や情報は避難所から入手して生活します。
最寄りの避難所で避難者としての登録を済ませ、自宅で過ごしながら、ライフラインの復旧を待ちましょう。水は給水拠点や配給車から、救援物資や情報は避難所から入手して生活します。
車の場合
避難者として登録した後は、愛猫と車の中での生活を選ぶ人も少なくありません。猫にとっても、見知らぬ場所で見知らぬ犬猫と過ごすよりストレスが少なく、プライバシーが保たれるというメリットもあります。
注意が必要なのはエコノミー症候群と熱中症で、いずれも命に関わります。
飼い主も猫も、1日数回は車外に出て運動するように心がけましょう。また、車中の温度には常に注意を払い、十分な飲み水を用意します。
注意が必要なのはエコノミー症候群と熱中症で、いずれも命に関わります。
飼い主も猫も、1日数回は車外に出て運動するように心がけましょう。また、車中の温度には常に注意を払い、十分な飲み水を用意します。
参考文献
人とペットの災害対策ガイドライン(避難中のペットの飼養環境の確保)(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h3002/0-full.pdf#page=52)
ペット防災に対する取り組み

東日本大震災をきっかけに、環境省では「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」を策定しました。そこでは、飼い主の責任によるペットとの同行避難を基本としています。
各自治体では、災害に備えて学校や公民館、公園などを避難場所や避難所として指定しています。
避難場所や避難所、またその周辺の状況はハザードマップで確認できます。また、自宅の浸水深など、災害リスクをピンポイントで確認することも可能です。
避難所でのペット対応は各自治体によって異なります。
最近では、ペット同行避難を含めた避難訓練をおこなっている自治体もあります。また、動物愛護センターや保健所の取り組みで、防災関連のイベントを開催する地域も増えてきました。
近所の人や猫つながりの友人とのコミュニケーションを大切にし、地域の防災訓練などに積極的に顔を出すことも、災害に対する備えです。
居住地域の情報も常に最新版を把握できるようにしておきましょう。
各自治体では、災害に備えて学校や公民館、公園などを避難場所や避難所として指定しています。
避難場所や避難所、またその周辺の状況はハザードマップで確認できます。また、自宅の浸水深など、災害リスクをピンポイントで確認することも可能です。
避難所でのペット対応は各自治体によって異なります。
最近では、ペット同行避難を含めた避難訓練をおこなっている自治体もあります。また、動物愛護センターや保健所の取り組みで、防災関連のイベントを開催する地域も増えてきました。
近所の人や猫つながりの友人とのコミュニケーションを大切にし、地域の防災訓練などに積極的に顔を出すことも、災害に対する備えです。
居住地域の情報も常に最新版を把握できるようにしておきましょう。
参考文献
人とペットの災害対策ガイドライン(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h3002/0-full.pdf)
まとめ

もしものことが起こったときに、愛猫と無事避難するための防災対策。
普段から意識して取り組み、準備しておけることが多くあります。備えあれば憂いなし。ペットの防災について考え、シミュレーションをおこない、常日ごろ準備を整えておくと安心です。
いざというときに愛猫と一緒にスムーズに避難できるよう、早速今日から準備をはじめましょう。
普段から意識して取り組み、準備しておけることが多くあります。備えあれば憂いなし。ペットの防災について考え、シミュレーションをおこない、常日ごろ準備を整えておくと安心です。
いざというときに愛猫と一緒にスムーズに避難できるよう、早速今日から準備をはじめましょう。