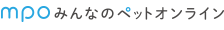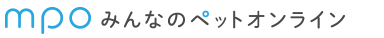猫は夜行性ではない

猫は薄明薄暮性の動物
夜に活発になるイメージを持たれている猫ですが、実際は、夜行性でも昼行性でもなく「薄明薄暮性(はくめいはくぼせい・クリパスキュラー)」です。
主に薄明(明け方)と薄暮(夕暮れ)の時間帯にもっとも活発に活動することを指しています。
猫以外の動物では、犬やウサギなども「薄明薄暮性」であるといわれています。
主に薄明(明け方)と薄暮(夕暮れ)の時間帯にもっとも活発に活動することを指しています。
猫以外の動物では、犬やウサギなども「薄明薄暮性」であるといわれています。
長時間睡眠をとるが、眠りは浅い
猫の語源は「寝子(ねこ)」であるという説があるほど、よく眠る動物です。
日中の大半をゴロゴロと寝て過ごしているように見えますが、実際昼間の眠りはさほど深くなく、いわゆる“うたた寝”が多いとされています。これはかつて猫が狩りをして暮らしていたとき、いざという場面で動けるよう体力を温存していた名残です。
猫の獲物となる鳥は明け方に、またネズミは夕暮れの時間から活発に動きだします。「薄明薄暮性」の猫の生態にもぴったり合うというわけです。
日中の大半をゴロゴロと寝て過ごしているように見えますが、実際昼間の眠りはさほど深くなく、いわゆる“うたた寝”が多いとされています。これはかつて猫が狩りをして暮らしていたとき、いざという場面で動けるよう体力を温存していた名残です。
猫の獲物となる鳥は明け方に、またネズミは夕暮れの時間から活発に動きだします。「薄明薄暮性」の猫の生態にもぴったり合うというわけです。
夜行性と勘違いされる理由

人間より暗いところがよく見えるから
猫といえば、暗闇でもらんらんと目を光らせている生き物。
猫の網膜の下には、入ってきた光を反射するタペタム層と呼ばれる層があります。これが反射板の役割を果たし、暗闇でもわずかな光があれば対象物を知覚できるようになっています。
猫が“夜目がきく”のは、このタペタム層の働きによるものなのです。この特性は、夜に狩りをする夜行性の動物や、深海魚などにも見られます。
猫の網膜の下には、入ってきた光を反射するタペタム層と呼ばれる層があります。これが反射板の役割を果たし、暗闇でもわずかな光があれば対象物を知覚できるようになっています。
猫が“夜目がきく”のは、このタペタム層の働きによるものなのです。この特性は、夜に狩りをする夜行性の動物や、深海魚などにも見られます。
夜活発に活動しているように感じるから
夜に愛猫がドタバタと室内を走り回る“夜の運動会”に遭遇したりしたことのある人は、「猫は日中は寝ていて、夜になると活発になる」というイメージを持つことでしょう。
実際には夜だから活発になっているのではなく、「日中退屈に過ごして、体力が余ってしまった」「急に思い立って運動不足やストレスを解消しようとしている」などの理由から、一時的に騒いでいることが多いようです。
実際には夜だから活発になっているのではなく、「日中退屈に過ごして、体力が余ってしまった」「急に思い立って運動不足やストレスを解消しようとしている」などの理由から、一時的に騒いでいることが多いようです。
ネコ科の動物に夜行性の動物がいるから
同じネコ科に分類されるトラやヒョウ、ジャガーなどは、暗闇の中で狩りをする夜行性の動物です。
そのため「ネコ科の肉食獣=夜行性」というイメージを持たれがちですが、同じネコ科であっても、猫とトラとでは生活様式が異なります。
そのため「ネコ科の肉食獣=夜行性」というイメージを持たれがちですが、同じネコ科であっても、猫とトラとでは生活様式が異なります。
夜の猫の行動

夜中に飼い主を起こす
寝ているところにのしかかってきたり、甘噛みやペロペロ攻撃を仕掛けてきたりする行動。そのしぐさはかわいいものの、夜は寝かせてほしいと思う飼い主も多いようです。
夜に駆け回る
猫が夜中に室内を走り回る行動は、“猫の運動会”とも呼ばれています。
唸り声を上げながら走る子もおり、飼い主の快眠の妨げになるケースも少なくありません。
唸り声を上げながら走る子もおり、飼い主の快眠の妨げになるケースも少なくありません。
夜になるとニャーニャー鳴き出す
飼い主が寝静まった深夜、起きて鳴き出す猫もいます。
これが続くと飼い主さんが寝不足になるだけでなく、ご近所トラブルに発展してしまう可能性もあります。
これが続くと飼い主さんが寝不足になるだけでなく、ご近所トラブルに発展してしまう可能性もあります。
猫が夜活発になる主な原因

発情期
猫は早くて生後6か月ごろに初めての発情期を迎えます。
去勢・避妊手術を受けていない猫は、発情期を迎えると大声で鳴きながらパートナーを探しまわったり、マーキングしたりする姿が見られるようになります。
室内にメス(オス)がいなくとも、野良猫のフェロモンに誘われて反応してしまうケースもあります。
去勢・避妊手術を受けていない猫は、発情期を迎えると大声で鳴きながらパートナーを探しまわったり、マーキングしたりする姿が見られるようになります。
室内にメス(オス)がいなくとも、野良猫のフェロモンに誘われて反応してしまうケースもあります。
運動不足
去勢・避妊手術を受けた猫は発情鳴きをしなくなりますが、夜中の“運動会”は変わらず開催されるケースがあります。
この行動の理由は諸説ありますが、昼間発散するはずのエネルギーがありあまっているために、夜の大騒ぎにつながっているという見方もあります。
この行動の理由は諸説ありますが、昼間発散するはずのエネルギーがありあまっているために、夜の大騒ぎにつながっているという見方もあります。
ストレス
環境の変化などでストレスを抱えた猫は、夜中に動き回ることで発散しようとするケースがあります。
先ほどの「運動不足」がストレスの原因になっていることも考えられます。
そのほかにも、居住スペースの騒音や振動が気になって安心できない、寝床の寝心地が悪い、同居猫や犬との折り合いが悪い、飼い主さんがあまり構ってくれない…など、ストレスの原因となるものはたくさんあります。
先ほどの「運動不足」がストレスの原因になっていることも考えられます。
そのほかにも、居住スペースの騒音や振動が気になって安心できない、寝床の寝心地が悪い、同居猫や犬との折り合いが悪い、飼い主さんがあまり構ってくれない…など、ストレスの原因となるものはたくさんあります。
催促
おなかがすいていると、ごはんをもらおうと飼い主を起こしに来ることもあります。
夜中に鳴いたり、飼い主の顔をなめたりするのは、食事を求めるサインかもしれません。
また、トイレが汚い場合にも、飼い主にアピールすることがあります。
夜中に鳴いたり、飼い主の顔をなめたりするのは、食事を求めるサインかもしれません。
また、トイレが汚い場合にも、飼い主にアピールすることがあります。
猫の夜の活動を防止するためには

去勢や避妊をする
猫が夜中に起き出すのは発情期が関係している場合があります。去勢や避妊手術を行うことで、問題行動の大半は抑制できます。手術の時期は、できれば生後6か月ごろ、はじめての発情期を迎える前に済ませるのが理想です。
運動させる
運動不足が考えられる場合は、昼間にたっぷり体を動かさせるのが有効です。
猫じゃらしやおもちゃを使って一緒に遊ぶ時間を設けると同時に、室内でも運動ができるよう、キャットタワーを設置するのがおすすめです。
必要な運動量は月齢や猫種によりさまざま。猫の体調を考慮しながら、十分な運動時間を確保してあげてくださいね。
猫じゃらしやおもちゃを使って一緒に遊ぶ時間を設けると同時に、室内でも運動ができるよう、キャットタワーを設置するのがおすすめです。
必要な運動量は月齢や猫種によりさまざま。猫の体調を考慮しながら、十分な運動時間を確保してあげてくださいね。
寝る前にごはんを与える
夜中に飼い主さんを起こしにくる猫は、おなかがすいている可能性があります。
できれば寝る前の決まった時間にごはんを与え、夜中におなかをすかせることがないように調節してあげるといいでしょう。
夜のごはんの要求にかまっていると、寝ているところを起こすのが当たり前になってしまうケースもあります。そうならないためにも、食事の時間はしっかりコントロールしましょう。
できれば寝る前の決まった時間にごはんを与え、夜中におなかをすかせることがないように調節してあげるといいでしょう。
夜のごはんの要求にかまっていると、寝ているところを起こすのが当たり前になってしまうケースもあります。そうならないためにも、食事の時間はしっかりコントロールしましょう。
トイレをきれいにしておく
猫はきれい好きな動物です。トイレが汚れているとストレスを感じ、「トイレをきれいにしてほしい」と飼い主にアピールする猫もいます。
就寝前にトイレを清潔にしておくことで、飼い主を起こしに来る行動が減っていくかもしれません。
就寝前にトイレを清潔にしておくことで、飼い主を起こしに来る行動が減っていくかもしれません。
まとめ

意外と知られていない本当の猫の生活形態や、夜行性ではないのに夜に活動的になる猫への対処法を説明しました。
発情期や運動不足、ストレスなど、本来は「薄明薄暮性」の猫が夜行性のようになってしまう理由はさまざまです。猫がストレスに感じることを減らし、自分たちの安眠を取り戻すためにも、正しい対処をおこないましょう。
関連する記事
発情期や運動不足、ストレスなど、本来は「薄明薄暮性」の猫が夜行性のようになってしまう理由はさまざまです。猫がストレスに感じることを減らし、自分たちの安眠を取り戻すためにも、正しい対処をおこないましょう。