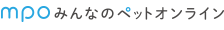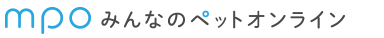猫の分離不安症とは

分離不安症とは、猫が飼い主と離れることに対して過剰な不安を感じる状態のこと。
猫は独立心のある動物と思われがちですが、実際には飼い主との絆を強く感じる子もいます。人懐っこく、飼い主のそばで過ごすことに喜びを感じる猫は意外に多いものです。
このような猫の場合、飼い主が外出したり、ほかの部屋へ移動したりと、家族の姿が見えなくなった途端に、ストレス行動が表れることがあります。たとえば、過剰な鳴き方、破壊行動、食欲不振などがあげられ、これらは分離不安症のサインといえます。
ストレス行動がみられたときは、その原因を探り、適切な対策をとってあげることが大切です。そのままにしておくと、時に長期的な行動問題や健康問題につながる可能性が出てきます。
猫は独立心のある動物と思われがちですが、実際には飼い主との絆を強く感じる子もいます。人懐っこく、飼い主のそばで過ごすことに喜びを感じる猫は意外に多いものです。
このような猫の場合、飼い主が外出したり、ほかの部屋へ移動したりと、家族の姿が見えなくなった途端に、ストレス行動が表れることがあります。たとえば、過剰な鳴き方、破壊行動、食欲不振などがあげられ、これらは分離不安症のサインといえます。
ストレス行動がみられたときは、その原因を探り、適切な対策をとってあげることが大切です。そのままにしておくと、時に長期的な行動問題や健康問題につながる可能性が出てきます。
猫が分離不安症になったときの症状をチェック

猫が分離不安症になると次のような症状がみられます。
これらの症状は、飼い主のいない留守中に起こることも多く、そのためすぐに気付けない場合もあります。
帰宅後に家具が傷ついていたり、物が散らかっていたり壊れていたりしていたら、注意して愛猫の様子を確認しましょう。分離不安を発症し、留守番中に症状が表れている可能性があります。
嘔吐のあとがあったり、食欲不振になったりしたときも要注意。愛猫の行動や様子に違和感があれば、できるだけ早く動物病院に相談しましょう。
ただし、嘔吐や脱毛、トイレの粗相などの症状は、ほかの病気からくる症状の可能性もあります。
まずは、愛猫に見られる症状が、分離不安症によるものなのか、他の病気によるものなのかを突き止めましょう。自己判断は禁物です。
関連する記事
- 飼い主が外出する際や留守中に鳴き続ける
- 家具や物を引っかく、噛む、破壊する
- トイレを失敗する
- 過剰なグルーミング(脱毛、炎症)
- 食欲不振または過食
- 通常より嘔吐が増える
- 飼い主の帰宅時に過剰に興奮する
- 常に飼い主のあとをついてくる
これらの症状は、飼い主のいない留守中に起こることも多く、そのためすぐに気付けない場合もあります。
帰宅後に家具が傷ついていたり、物が散らかっていたり壊れていたりしていたら、注意して愛猫の様子を確認しましょう。分離不安を発症し、留守番中に症状が表れている可能性があります。
嘔吐のあとがあったり、食欲不振になったりしたときも要注意。愛猫の行動や様子に違和感があれば、できるだけ早く動物病院に相談しましょう。
ただし、嘔吐や脱毛、トイレの粗相などの症状は、ほかの病気からくる症状の可能性もあります。
まずは、愛猫に見られる症状が、分離不安症によるものなのか、他の病気によるものなのかを突き止めましょう。自己判断は禁物です。
猫の分離不安症の原因

環境の変化
猫はデリケートな動物です。
引っ越しなど住環境の変化や、新しい家族が増えるといった家族構成の変化は、分離不安症の原因となることがあります。
住む場所が変わらなくても、飼い主の転職などによる生活リズムの変化や、同居ペットとの死別なども猫に大きなストレスを与え、分離不安症の引き金になる場合があります。
引っ越しなど住環境の変化や、新しい家族が増えるといった家族構成の変化は、分離不安症の原因となることがあります。
住む場所が変わらなくても、飼い主の転職などによる生活リズムの変化や、同居ペットとの死別なども猫に大きなストレスを与え、分離不安症の引き金になる場合があります。
孤独感や退屈感
ひとりで過ごす時間を楽しむ猫は多いですが、なかには飼い主の気配がないと不安になってしまう子もいます。
長時間の留守番、飼い主の不在時に抱く不安感や孤独感、飼い主とのコミュニケーション不足が、分離不安症を引き起こす原因になることもあります。
長時間の留守番、飼い主の不在時に抱く不安感や孤独感、飼い主とのコミュニケーション不足が、分離不安症を引き起こす原因になることもあります。
過去のトラウマ
留守中に大きな音がしたり、家具が倒れたりと、危険な目にあった経験が原因となることも。過去の恐怖体験がトラウマとなり、飼い主の不在時に「また同じようなことが起こるのでは」と不安を感じているケースも考えられます。
飼い主との依存関係
猫が単身の飼い主と暮らしている場合、飼い主への依存心が強くなる可能性があります。
一方で、同居家族が多い場合でも、ひとりで過ごす経験が少ないために、留守番時に不安を感じやすいケースも見られます。
過剰な依存心は、飼い主と離れることへの不安を引き起こし、分離不安症の原因にもつながります。
一方で、同居家族が多い場合でも、ひとりで過ごす経験が少ないために、留守番時に不安を感じやすいケースも見られます。
過剰な依存心は、飼い主と離れることへの不安を引き起こし、分離不安症の原因にもつながります。
飼い主の生活リズムが不規則
飼い主の外出や帰宅時間が毎日異なると、猫は「いつ飼い主がいなくなるのか」「いつ帰ってくるのか」が分からず、ストレスを感じてしまいます。
飼い主が家にいる時間や一緒に遊ぶ時間、食事の時間などはできるだけ規則正しいほうがよいでしょう。
飼い主が家にいる時間や一緒に遊ぶ時間、食事の時間などはできるだけ規則正しいほうがよいでしょう。
加齢、病気
加齢によって視覚や聴覚、体力が低下すると、不安を感じやすくなります。
また、認知症のような病気が分離不安症の引き金になるケースも少なくありません。
これまで問題なく留守番できていたのに、突然できなくなったとしたら、加齢や病気が原因になっているかもしれません。
また、認知症のような病気が分離不安症の引き金になるケースも少なくありません。
これまで問題なく留守番できていたのに、突然できなくなったとしたら、加齢や病気が原因になっているかもしれません。
分離不安症になりやすい猫の特徴

分離不安症になる原因は、性格や育て方、年齢など、さまざまな要素が関係します。
たとえば、母猫や兄弟猫と離れるのが早く、飼い主が親猫代わりになっている場合は分離不安症になりやすいといえます。
また、飼い主と常に一緒にいたり、トイレやお風呂など飼い主がどこへ行くにもついてきたりする状況であれば、すでに離れるのが難しくなっているかもしれません。
年齢でいうと、若い猫のほうが発症しやすく、1歳くらいまでの経験が原因となるケースが多い傾向にあります。子猫期の体験や出来事、環境そのものが積み重なって、分離不安症の引き金となるのです。
愛猫の性格やとりまく環境が以下の内容に当てはまる場合は、分離不安症になりやすいので注意が必要です。
たとえば、母猫や兄弟猫と離れるのが早く、飼い主が親猫代わりになっている場合は分離不安症になりやすいといえます。
また、飼い主と常に一緒にいたり、トイレやお風呂など飼い主がどこへ行くにもついてきたりする状況であれば、すでに離れるのが難しくなっているかもしれません。
年齢でいうと、若い猫のほうが発症しやすく、1歳くらいまでの経験が原因となるケースが多い傾向にあります。子猫期の体験や出来事、環境そのものが積み重なって、分離不安症の引き金となるのです。
愛猫の性格やとりまく環境が以下の内容に当てはまる場合は、分離不安症になりやすいので注意が必要です。
- 甘えん坊
- シャイで臆病な性格
- 家族のなかで唯一のペット
- ひとりで過ごすことに慣れていない
- 過去にトラウマを持っている
- 大きな生活環境の変化があった(引っ越し、家族構成の変化)
- 高齢や病気である
分離不安症の治し方や対策

留守番に慣れさせる
もっとも効果が期待できる基本的な対策で、最初に取り組みたい方法です。
愛猫がひとりで過ごすことに慣れるよう、短時間の留守番からはじめてみましょう。徐々に時間を延ばし、少しずつ長い時間も落ち着いて過ごせるようトレーニングします。
重要なのは、留守番が「特別なこと」ではなく、「日常の一部」であると愛猫に感じてもらうことです。極端にいうと「気付けば飼い主がいなくなっていた」と思えるような自然な状態を作れれば理想的です。
外出する際は、出かけることを意識させないようにしましょう。飼い主が外出を強調する仕草を避け、できるだけ刺激を与えず、静かに玄関を出るのがポイントです。
関連する記事
愛猫がひとりで過ごすことに慣れるよう、短時間の留守番からはじめてみましょう。徐々に時間を延ばし、少しずつ長い時間も落ち着いて過ごせるようトレーニングします。
重要なのは、留守番が「特別なこと」ではなく、「日常の一部」であると愛猫に感じてもらうことです。極端にいうと「気付けば飼い主がいなくなっていた」と思えるような自然な状態を作れれば理想的です。
外出する際は、出かけることを意識させないようにしましょう。飼い主が外出を強調する仕草を避け、できるだけ刺激を与えず、静かに玄関を出るのがポイントです。
安心して過ごせる環境をつくる
愛猫がリラックスでき、安心して留守番ができるよう、心地よい環境を整えましょう。静かで落ち着ける場所に、お気に入りのベッドやマットを置いたり、四方を囲んだスペースを用意したりするのが効果的です。
また、キャットタワーやハンモック、ステップなどを設置するのもおすすめです。
お気に入りのテリトリーが多いのはよいことで、猫があちこちに移動できる環境はストレスの軽減につながります。
さらに、留守番中の退屈を避けるために、ひとりでも遊べるおもちゃも準備するとよいでしょう。誤飲の可能性がある紐状のものは避け、ひとりで長時間遊べる知育玩具タイプがおすすめです。
関連する記事
また、キャットタワーやハンモック、ステップなどを設置するのもおすすめです。
お気に入りのテリトリーが多いのはよいことで、猫があちこちに移動できる環境はストレスの軽減につながります。
さらに、留守番中の退屈を避けるために、ひとりでも遊べるおもちゃも準備するとよいでしょう。誤飲の可能性がある紐状のものは避け、ひとりで長時間遊べる知育玩具タイプがおすすめです。
習慣を変える
どの家庭でも留守番時間をゼロにするのは不可能です。そこで、飼い主の不在時と在宅時の差をなるべく少なくする工夫をしてみましょう。
まず、一緒にいるときは過剰に構い過ぎないよう注意が必要です。いつでもどこでもそばに寄り添うのは避けましょう。
外出時や帰宅時は、大げさに声をかけたり、愛猫を興奮させたりしないことが大切です。
まず、一緒にいるときは過剰に構い過ぎないよう注意が必要です。いつでもどこでもそばに寄り添うのは避けましょう。
外出時や帰宅時は、大げさに声をかけたり、愛猫を興奮させたりしないことが大切です。
専門家にアドバイスをもらう
さまざまな対策を試しても改善しない場合は、動物病院で相談しましょう。
愛猫の分離不安症が重度の場合は、抗うつ剤などを用いた薬物療法が検討されることも。薬物療法は効果が得られるまでに2カ月程度かかる場合もあり、服用を継続する必要があります。
薬の使用に関しては、必ず獣医師の指示に従いましょう。
なお、薬物療法はメインの対策ではなく、行動療法を補助する目的で取り入れられることが多いです。
関連する記事
愛猫の分離不安症が重度の場合は、抗うつ剤などを用いた薬物療法が検討されることも。薬物療法は効果が得られるまでに2カ月程度かかる場合もあり、服用を継続する必要があります。
薬の使用に関しては、必ず獣医師の指示に従いましょう。
なお、薬物療法はメインの対策ではなく、行動療法を補助する目的で取り入れられることが多いです。
まとめ

分離不安症を防ぐためには、愛猫が飼い主と離れている時間も安心して過ごせるような環境づくりが大切です。過剰に構い過ぎることを避け、外出時や帰宅時も平常心を保つよう心がけましょう。
もし分離不安の症状がみられる場合は、原因を見極め、この記事で紹介した対策を試してみてください。日ごろから愛猫の不安を軽減してあげられるように工夫してみましょう。
関連する記事
もし分離不安の症状がみられる場合は、原因を見極め、この記事で紹介した対策を試してみてください。日ごろから愛猫の不安を軽減してあげられるように工夫してみましょう。