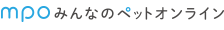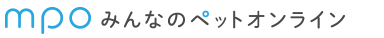発情期とは

発情期の仕組み
発情とは、猫が繁殖のために本能的に示す行動のことを指します。
体が成熟し、繁殖可能な状態になると発情期を迎えます。個体差が大きいですが、はじめての発情期は生後6カ月から12カ月ごろに迎えるといわれています。
体が成熟し、繁殖可能な状態になると発情期を迎えます。個体差が大きいですが、はじめての発情期は生後6カ月から12カ月ごろに迎えるといわれています。
発情期の時期と頻度
猫は長日繁殖動物です。「長日」とは日照時間のことで、日が長くなる春から秋にかけての期間が繁殖期となる動物のことを指します。
繁殖期を迎えると、猫は発情行動を示します。一度のサイクルは約1週間で、3週間ごとに繰り返されます。
室内飼いの猫は、照明や暖房の影響で一年中長日状態となり、発情が続くこともあります。
繁殖期を迎えると、猫は発情行動を示します。一度のサイクルは約1週間で、3週間ごとに繰り返されます。
室内飼いの猫は、照明や暖房の影響で一年中長日状態となり、発情が続くこともあります。
発情期の猫の行動
メス

発情鳴き
発情鳴きは、猫の発情行動のなかでもよく知られているものの一つといえるでしょう。
鳴き声は、発情期特有の高く大きな声で、遠くまで響き渡ります。これは、メス猫がオス猫に存在を知らせるための行動です。
鳴き声は、発情期特有の高く大きな声で、遠くまで響き渡ります。これは、メス猫がオス猫に存在を知らせるための行動です。
特有の姿勢(ロードシス)
背中を反らせ、しっぽをピンと上にあげるポーズをとり、時にはそのまま後ろ足で足踏みすることもあります。このような姿勢を「ロードシス」といいます。
ロードシスは、発情期のピークに見られる本能的な行動の一つで、オス猫への交配サインです。
ロードシスは、発情期のピークに見られる本能的な行動の一つで、オス猫への交配サインです。
スプレー行為(マーキング)
いわゆるマーキング行為の一種で、トイレ以外の場所で排尿したり、壁に向かってスプレーのように勢いよく尿を吹き付けたりします。
主にオス猫がとる行動ですが、メス猫でも見られることがあります。
また、異性への存在をアピールするための行動であるため、尿は普段より濃く、臭いも強くなります。
主にオス猫がとる行動ですが、メス猫でも見られることがあります。
また、異性への存在をアピールするための行動であるため、尿は普段より濃く、臭いも強くなります。
飼い主に甘える
発情期特有の行動で、とくにメス猫に多く見られます。体をスリスリと飼い主にこすりつけたり、抱っこやスキンシップをせがんだりすることが増えます。
発情期の前期によく見られる行動です。
発情期の前期によく見られる行動です。
ソワソワと落ち着かなくなる
部屋の中を歩き回ったり、外に出たがったりするようになります。落ち着きがなくなり、突然駆け回ることも。
また、「ローリング」と呼ばれる、背中をこすり付けながら転げ回る行動も見られます。
また、「ローリング」と呼ばれる、背中をこすり付けながら転げ回る行動も見られます。
オス

スプレー行為(マーキング)
家具や壁に向かって、スプレーのように尿を吹き付ける行動が目立つようになります。
これは、テリトリーを示すための本能的な行動で、尿には強い臭いがあるのも特徴です。
これは、テリトリーを示すための本能的な行動で、尿には強い臭いがあるのも特徴です。
大きく鳴く
オス猫はメス猫を呼ぶために、低く大きな声で鳴きます。メス猫と比較するとトーンが低い点が特徴で、夜間も頻繁に鳴くことがあります。
この行動は、発情期のピークに見られます。
この行動は、発情期のピークに見られます。
脱走
発情期になると、オス猫はメス猫を探し求める行動をとるようになります。
そのため、部屋の外や玄関から外へ出たがる様子が見られるでしょう。
そのため、部屋の外や玄関から外へ出たがる様子が見られるでしょう。
攻撃的な行動
縄張り争いによって攻撃的になることがあります。オス猫同士はもちろん、飼い主に対して威嚇したり、引っかいたりすることも。
食欲の減退
発情期中は、食事よりも繁殖行動に意識が向くため、食欲が落ちることがあります。
発情期中の対処法

鳴き声
発情期の鳴き声は生理現象によるもので、完全にやめさせることはできません。しかし、近隣への影響を抑える工夫は可能です。
周囲に鳴き声が響きにくくなるよう、部屋の機密性を高めましょう。防音効果のある壁紙やカーテン、窓に貼るシートなどを活用すると効果的です。
夜鳴きが気になる場合は、日中に十分は運動をさせて疲れさせ、猫がぐっすり眠れる状態にさせるのも有効です。
関連する記事
周囲に鳴き声が響きにくくなるよう、部屋の機密性を高めましょう。防音効果のある壁紙やカーテン、窓に貼るシートなどを活用すると効果的です。
夜鳴きが気になる場合は、日中に十分は運動をさせて疲れさせ、猫がぐっすり眠れる状態にさせるのも有効です。
猫は夜行性じゃなかった? 猫が夜活動する理由と対策
猫が夜行性と勘違いされる原因や、実際の生活スタイルについて説明します。また、「猫が夜に暴れて困っている」飼い主さんに向けて、対処方法もご紹介します。
スプレー行為
発情期中のスプレー行為(マーキング)もやめさせることは難しいですが、対策を講じることで被害を抑えられます。
スプレーされやすい場所にトイレを設置するほか、防水シートを貼るのもおすすめです。
マーキングによる汚れを見つけたら、できるだけすぐに掃除をしましょう。
スプレーされやすい場所にトイレを設置するほか、防水シートを貼るのもおすすめです。
マーキングによる汚れを見つけたら、できるだけすぐに掃除をしましょう。
脱走
普段は外に興味を示さない猫でも、発情期になると本能的に異性の猫を探そうとし、脱走のリスクが高まります。
窓やドアは飼い主が意識してしっかりと閉めましょう。玄関やベランダ、窓などに、柵やロックなどの脱走防止グッズを活用するのも一つの方法です。
また、玄関付近に近づけないようにするのもよいでしょう。
万が一のために、マイクロチップの装着や首輪・迷子札をつけるなど、身元が分かるようにしておくことをおすすめします。
窓やドアは飼い主が意識してしっかりと閉めましょう。玄関やベランダ、窓などに、柵やロックなどの脱走防止グッズを活用するのも一つの方法です。
また、玄関付近に近づけないようにするのもよいでしょう。
万が一のために、マイクロチップの装着や首輪・迷子札をつけるなど、身元が分かるようにしておくことをおすすめします。
避妊・去勢手術を受けるメリット

発情期中の鳴き声やスプレー行為は、メス猫は避妊手術、オスは去勢手術を受けることで抑えられます。
手術のタイミングは、はじめての発情期を迎える前の生後6カ月前後が理想的です。発情を抑え、病気のリスクを減らすメリットがあるためです。
はじめての発情期を迎えたあとでも手術は可能で、発情期中の行動を完全ではないものの抑える効果が期待できます。
このようにメリットの多い避妊・去勢手術ですが、手術のリスクも伴うため、適切な時期について獣医師に相談しましょう。
避妊・去勢手術の具体的なメリットには、次のようなものがあります。
手術のタイミングは、はじめての発情期を迎える前の生後6カ月前後が理想的です。発情を抑え、病気のリスクを減らすメリットがあるためです。
はじめての発情期を迎えたあとでも手術は可能で、発情期中の行動を完全ではないものの抑える効果が期待できます。
このようにメリットの多い避妊・去勢手術ですが、手術のリスクも伴うため、適切な時期について獣医師に相談しましょう。
避妊・去勢手術の具体的なメリットには、次のようなものがあります。
発情期特有の行動の減少
生理現象である発情鳴きやスプレー行為は、避妊・去勢手術によって軽減、または消失します。
とくに発情鳴きは声が大きく、昼夜問わず鳴くため、飼い主にとって大きな悩みの種となることも。発情鳴きがなくなるだけでも、手術をするメリットはあるといえるでしょう。
とくに発情鳴きは声が大きく、昼夜問わず鳴くため、飼い主にとって大きな悩みの種となることも。発情鳴きがなくなるだけでも、手術をするメリットはあるといえるでしょう。
猫自身の健康維持
メス猫は子宮や卵巣の病気(子宮蓄膿症、卵巣腫瘍など)、オス猫であれば前立腺炎などの生殖器関連の病気予防につながります。
飼い主と猫の生活の質向上
猫にとっても生理現象とはいえ、異性を求めて鳴き続けたり、攻撃的になったりするのは、疲労やストレスの原因につながります。
また、飼い主も近隣への配慮やマーキング汚れの掃除に追われ、発情期は大きな負担となります。
これらの問題が解消されれば、季節問わず落ち着いた生活ができるようになるでしょう。
関連する記事
また、飼い主も近隣への配慮やマーキング汚れの掃除に追われ、発情期は大きな負担となります。
これらの問題が解消されれば、季節問わず落ち着いた生活ができるようになるでしょう。
まとめ

発情期の行動は本能によるもので、完全にやめさせることは難しいものです。しかし、適切な対策を講じることで、負担を軽減できます。
発情行動へのもっとも有効な対策は、適切な時期に避妊・去勢手術をおこなうことです。手術には多くのメリットがありますが、リスクも伴うため、早めにかかりつけの獣医師に相談しましょう。
発情行動へのもっとも有効な対策は、適切な時期に避妊・去勢手術をおこなうことです。手術には多くのメリットがありますが、リスクも伴うため、早めにかかりつけの獣医師に相談しましょう。