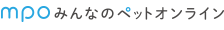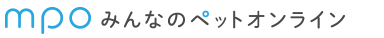猫は子どもが苦手?

猫は子どもが苦手なわけではなく、予測不可能な行動をとる人が苦手なのです。もともと警戒心の強い動物なので、大きな声を出したり走って近づいたりすると驚いて逃げてしまいます。 “猫は子どもが苦手”といわれるゆえんは、ここにあるのです。
猫は子どものこんなところが苦手
動きが速い
いきなり駆け寄っていく、遊んでいるつもりで追いかけ回すなど、一緒に遊びたくて子どもがした行動でも猫にとってはストレスと感じることも……。また、年齢の低い子どもほど猫と目線の高さが近くなるため、視線を強く感じます。目線を合わせることは猫にとって威嚇のサインとなるため、警戒心が生まれてしまうのです。
突然、大声をあげる
人間よりも聴力の優れている猫にとって、突然の大声は驚くと同時に不快でもあります。威嚇されていると感じることもあるので、警戒心を解くことができません。
頻繁に大声を出す相手を認識すると、その人の顔を見ただけで逃げるようになってしまう可能性もあります。
頻繁に大声を出す相手を認識すると、その人の顔を見ただけで逃げるようになってしまう可能性もあります。
触り方が乱暴、雑
乳幼児は特に、猫を触る加減がまだ分からないこともあるでしょう。子どもはソフトタッチなつもりでも、猫にとっては強すぎる場合もあります。また、小さな子どもはつい猫の長いしっぽを引っ張りたくなってしまうようですが、骨や神経などがあるしっぽは猫の急所でもあるため嫌がります。
ものをひっくり返したり、投げたりする
おもちゃ箱やランドセルの中身をひっくり返して出すといった行為も、大きな音が出ますよね。子どもが普段からしている何気ない行為も、猫にとっては「怖い」と感じる不安材料になることがあります。猫と遊びたいからとおもちゃを投げるようなことも、猫は攻撃されたと感じてしまいます。
子どもが何歳くらいから猫を迎えるのがいい?
明確な基準はありませんが、子どもの年齢が低いほど注意すべきことは多く、「子どもが小学生のころ」をベストなタイミングととらえる家族は多いようです。
乳児や床に手を付くことの多いハイハイの時期の子どもは、衛生面や猫用品の誤飲などに気をつける必要があります。子どもが4~5歳くらいになれば、餌をあげるといったような簡単な世話をできるようになるでしょう。また、“ペットは生き物で大事にしなくてはならない存在”ということも理解できる年齢なので、猫を迎える上での心配事は少なくなります。
乳児や床に手を付くことの多いハイハイの時期の子どもは、衛生面や猫用品の誤飲などに気をつける必要があります。子どもが4~5歳くらいになれば、餌をあげるといったような簡単な世話をできるようになるでしょう。また、“ペットは生き物で大事にしなくてはならない存在”ということも理解できる年齢なので、猫を迎える上での心配事は少なくなります。
猫と子どもの距離を縮める方法

小さい子どもがいる家庭で猫を迎える場合、注意すべきことは多いということをお伝えしました。しかし、子どもが大きくなるまで、猫は飼えないのかというと、そんなことはありません。
猫とのふれあい方を教えながら親が子どもと猫の関係性を注意して見守ることができれば、子どもの年齢に関わらず迎えることができます。
ここでは子どもと猫の関係性を良好に築くためのポイントをご紹介します。
猫とのふれあい方を教えながら親が子どもと猫の関係性を注意して見守ることができれば、子どもの年齢に関わらず迎えることができます。
ここでは子どもと猫の関係性を良好に築くためのポイントをご紹介します。
ふれあい方を教える
小さい子どもほど、ぬいぐるみと同じようにおもちゃの感覚で猫とふれあってしまうことは少なくありません。自分と同じように命があり、うれしいとか悲しいといった感情がある生き物であることを伝えましょう。
猫の習性や猫とふれあうときのルールも、最初に教えておくことが大切です。猫にさわるときは優しく、「眠っているときは、そっとしておいてあげようね」「猫がびっくりするから、大きな声や音を出さないように気をつけようね」など、具体的なアドバイスを与えると子どもも理解しやすいでしょう。
猫の習性や猫とふれあうときのルールも、最初に教えておくことが大切です。猫にさわるときは優しく、「眠っているときは、そっとしておいてあげようね」「猫がびっくりするから、大きな声や音を出さないように気をつけようね」など、具体的なアドバイスを与えると子どもも理解しやすいでしょう。
一緒に遊ぶ
一緒に遊び、子どもと猫が楽しさを共有することでその距離はグッと縮まります。猫用おもちゃの遊び方を親が教えた上で、一緒に遊ばせる時間を作りましょう。
猫は、ひもやリボンといったひらひらとしたもの、動くものが大好きです。けれど、誤飲や事故の心配もあるため子どもには猫用おもちゃ以外で遊ぶことは控えるように伝えておくのが安心です。
猫は、ひもやリボンといったひらひらとしたもの、動くものが大好きです。けれど、誤飲や事故の心配もあるため子どもには猫用おもちゃ以外で遊ぶことは控えるように伝えておくのが安心です。
子どもにごはん・おやつ係を担当してもらう
猫にごはんやおやつを与える役割を、子どもに与えましょう。“ごはんをくれる人”と猫が認識し、子どもに懐いてくれます。子どもも、役割を与えられることで責任感が生まれて「猫ともっと仲良くなりたい」という気持ちが芽生えます。
子どもと仲良くなれる猫の特徴

子どもに猫とのふれあい方を教えることが一番大事ではありますが、猫によってもそれぞれ性質が異なり、子どもと比較的うまく関係性を築ける特徴を備えた猫もいます。
子どもと相性のいい猫には、おとなしい・社交的・頭がいいなどの特徴があります。
子どもと相性のいい猫には、おとなしい・社交的・頭がいいなどの特徴があります。
おとなしい猫
子どもがいて、なおかつ猫を飼うのがはじめてという家庭で飼いやすいのが、おとなしく落ち着いた猫。マイペースに過ごすことができるので、子どもが騒いでもストレスを感じにくい性格です。また、人間との距離感を上手に保てるため引っかく・飛びつくといった攻撃が少なく、小さい子どもがいても安心でしょう。
もちろん、おとなしい猫であっても猫に過剰なストレスを与えないよう、子どもを導いてあげることは大切です。
関連する記事
もちろん、おとなしい猫であっても猫に過剰なストレスを与えないよう、子どもを導いてあげることは大切です。
社交的な猫
なかには抱っこはもちろん、触られることすら嫌がる猫もいます。頻繁に人にすり寄ってくる、なでると気持ちよさそうにしてじっとしている猫なら、人間とふれあうことが好きなタイプと考えていいでしょう。
人なつっこい性格の猫であれば子どもも猫への愛情が強くなり、より仲良くなれるはずです。
関連する記事
人なつっこい性格の猫であれば子どもも猫への愛情が強くなり、より仲良くなれるはずです。
頭がいい猫
トイレの場所をすぐ覚えてくれる、名前を呼ぶと反応を示すといった賢さのある猫はコミュニケーションがとりやすいものです。猫に気持ちが通じることが分かり、子どもはお世話をすることの楽しさを実感できるでしょう。
子どもと仲良くなれるおすすめの猫種

子どものいる家庭で飼いやすいのは、おとなしい・社交的・頭がいいといった特徴を持つ猫。けれど、ブリーダーやペットショップを見学中に、猫の性格まで見極めるのはなかなか難しいかもしれません。個体差はありますが、子どものいる家庭でも飼いやすいといわれる特徴をもつ、おすすめの猫種を紹介しましょう。
アメリカンショートヘア
独特の縞模様を持つ、短毛種。明るくフレンドリーで順応性が高いので、どんな家庭でも飼いやすい猫です。ネズミを狩るワーキングキャットとして活躍した歴史があり、動くものを捕まえずにはいられないという好奇心旺盛な特徴も持っています。遊ぶのが大好きなので、子どもともたくさん遊んでくれるでしょう。
販売中のアメリカンショートヘアの子猫を見る
関連する記事
スコティッシュフォールド
丸みを帯びたボディに、折れ耳がキュートな猫。“犬のような特徴をもつ”といわれるほど人なつっこく、人間とのコミュニケーションをとることに長けた賢い性格を持ちます。のんびり屋さんで環境の変化にも動じないので、子どもとの相性もばっちりです。
販売中のスコティッシュフォールドの子猫を見る
関連する記事
ラグドール
英語で“ぬいぐるみ”という名前の通り、人間に抱っこされるのが大好きな猫。おとなしく穏やかな性格なので、やさしく扱えば子どもにもよく懐いてくれるでしょう。
また、高いところに登ったり家具を爪で引っかいたりするようなことが少ないという特徴も持ちます。手触りのいいふさふさの毛並みをもちますが、換毛期を除いては見た目ほど抜け毛が少ないのでお手入れも比較的ラクです。
販売中のラグドールの子猫を見る
関連する記事
また、高いところに登ったり家具を爪で引っかいたりするようなことが少ないという特徴も持ちます。手触りのいいふさふさの毛並みをもちますが、換毛期を除いては見た目ほど抜け毛が少ないのでお手入れも比較的ラクです。
まとめ

猫は子どもが苦手なのではなく、不快に感じる行動をとる人が苦手です。猫には学習能力があるので一度、苦手意識を抱いてしまうとその気持ちを忘れさせることが難しくなってしまいます。
猫と子どもが仲良くなるためには、飼う前に猫の特徴を親がしっかり教えることが大切です。飼いはじめは親子で世話や遊び方を一緒に行い、子どもも猫も「一緒に過ごすと楽しいな」と思えるように少しずつ距離を縮めていきましょう。
関連する記事
猫と子どもが仲良くなるためには、飼う前に猫の特徴を親がしっかり教えることが大切です。飼いはじめは親子で世話や遊び方を一緒に行い、子どもも猫も「一緒に過ごすと楽しいな」と思えるように少しずつ距離を縮めていきましょう。