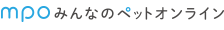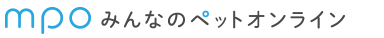良く耳にする「諺」を解説していきましょう。
まずは、
「猫に小判」
猫に小判とは、価値の分からない人に貴重なものを与えても何の役にも立たない事のたとえ。
「猫ばば」
《猫が、糞 (ふん) をしたあとを、砂をかけて隠すところから》悪いことを隠して素知らぬ顔をすること。また、拾得物などをこっそり自分のものとすること。「拾った物を猫糞(ババ)する」
「猫に鰹節」
猫のそばに好物の鰹節を置いておくのと同じくらい油断できないこと。危険な事。
(本当に猫ちゃんは、かつを節が好きなのかどうかはわかりません)
「猫を被る」
本性を隠して猫のように大人しくしているたとえ。知っていることを知らないかのように振る舞うという意味もあるようです。
「猫も杓子も」
「誰もかれも」という意味。杓子とは、ご飯やお味噌汁などをよそうしゃもじやお玉のこと。由来は諸説ありますが、しゃもじやお玉はよく目にするものだからとされています。
「新型コロナウィルスで、誰もがマスクをしていますね、そんな時に使うのはどうかな?」
「窮鼠猫を嚙む」
追いつめられたネズミが猫に噛み付くこと。どんなに弱い者でも、ピンチのときには反撃に出るという意味。
「猫にもなれば虎にもなる」
同じ人が、時と場合により猫のように大人しくも成り、又、場合によっては虎のように荒々しくもなるさま。
「鼠とる猫は爪隠す」
能力や力のある人は、それをむやみに誇示しないことのたとえ。同じ意味を持つことわざとしてより私たちに馴染み深いのは、「能ある鷹は爪を隠す」がありますね。
「鳴く猫は鼠を捕らぬ」
お喋りな人に限って、口先だけで行動しないという意味。
今の政治家、こんな感じかな?
本当に色々とありますね。では、海外ではどんな感じ。

「Curiosity killed the cat」
直訳では、「好奇心は猫を殺した」と成ります。
好奇心旺盛は身を滅ぼすことのたとえ。運動神経バツグンの猫も、好奇心によって高い所から下りられなくなったり、狭い隙間にはさまって出てこられなくなったりすることがあります。過剰な好奇心には気を付けるべきという戒めですね。
「Bell the cat」
直訳では、「猫に鈴」。みんなのために進んで危険なことに立ち向かうという意味です。イソップ物語の中で、ネズミたちが天敵である猫の首に鈴をつければ自衛ができると思いつき、誰がその鈴を付けるか思い悩んだ、その事でこの諺が生まれたと言われています。
色々と身近な諺にこれほど登場する動物は他に居ませんね、
それほど、人間との係わりがあった証拠です。
暇つぶしで、色々な諺や慣用句を調べるのも面白いものです。

 池田研司ブリーダーの子猫一覧
池田研司ブリーダーの子猫一覧













 関連記事
関連記事 ブログトップに戻る
ブログトップに戻る 最新記事
最新記事 人気の記事
人気の記事 カテゴリ
カテゴリ